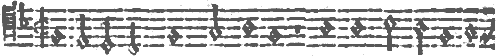 |
||
| 会衆讃美の歌唱スタイル ルター派の聖歌は会衆によるコラールと典礼文とがセットになったものでした。コラールは聖務日課を福音主義的に解釈しなおした教会暦によってレパートリーを増やしていきました。それらの聖歌の雛形になったのは中世を通じて歌い継がれた民謡や典礼歌でした。いずれの場合もドイツ語に訳される過程で、かつてのミンネゼンガーが広めたバール形式と呼ばれる詩形が用いられ、会衆が歌うにあたって複雑な形式をある程度整える役割を持たせています。しかし同じドイツでもゲルマン色の強い北ドイツとラテン語圏と接していた南ドイツでは文化の土壌が異なり、好まれる音楽にも違いがありました。さらには土地柄以外にも、身分制度の壁を隔てても音楽の嗜好が区分されていたと考えられます。今に例えれば宮廷と民衆との音楽の嗜好にはクラシックと演歌の違いくらいあったといえば判りやすいでしょうか。それだけ違和感のあることを16世紀の宗教改革は礼拝のなかでやってのけたのです。初期のコラールにはこうした文化的多様性を背景にもつ傾向が顕著です。  一方でカルヴァンの礼拝式は、スイスでの宗教改革の一環として教会暦を一度白紙に戻すことから出発したので、150の詩篇歌全てを一年に3〜4回のサイクルで歌うように考えられていました。カルヴァンは詩篇歌を策定するにあたって、フェラーラの宮廷で聴いたであろう鳥のさえずりを描写したマドリガルなど技巧的な歌を嫌っていたようですが、カトリックの典礼歌をそのまま用いるということもしませんでした。カルヴァンに協力したクレマン・マロはペトラルカ主義に魅入られたフランス語ソネットの達人であり、作曲のルイ・ブルジョワも押韻詩に相応しく、12世紀のトルヴェールにまで遡るような懐古的なメロディを付けました。これは当時最もルネサンス的な都市のひとつであったシュトラスブルクの例に倣ったものです。そこでは北イタリアでのフロットラやパヴァーヌといった歌謡や舞曲の形式に添った簡潔なメロディが好まれていましたが、それらは元を辿るとフランスの世俗歌謡にルーツをもつものです。 一方でカルヴァンの礼拝式は、スイスでの宗教改革の一環として教会暦を一度白紙に戻すことから出発したので、150の詩篇歌全てを一年に3〜4回のサイクルで歌うように考えられていました。カルヴァンは詩篇歌を策定するにあたって、フェラーラの宮廷で聴いたであろう鳥のさえずりを描写したマドリガルなど技巧的な歌を嫌っていたようですが、カトリックの典礼歌をそのまま用いるということもしませんでした。カルヴァンに協力したクレマン・マロはペトラルカ主義に魅入られたフランス語ソネットの達人であり、作曲のルイ・ブルジョワも押韻詩に相応しく、12世紀のトルヴェールにまで遡るような懐古的なメロディを付けました。これは当時最もルネサンス的な都市のひとつであったシュトラスブルクの例に倣ったものです。そこでは北イタリアでのフロットラやパヴァーヌといった歌謡や舞曲の形式に添った簡潔なメロディが好まれていましたが、それらは元を辿るとフランスの世俗歌謡にルーツをもつものです。ルターにせよカルヴァンにせよ、中世の文化を全否定した(ツヴィングリがそうでした)のではなく、むしろ大いに引き継いでいる面は見逃せません。しかし宗教改革の礼拝で突然、様々な身分の人々が一緒に声を合わせるのは容易なことではありませんでした。なかには調子外れな声で歌う人も居たでしょう。宗教改革の初期には先唱者を立てて会衆にメロディーを復唱させる方法をとりました。ルター派の聖歌隊が先唱の役目を担うための曲集には、フランドル風のポリフォニーに編まれたものとは別に、より旋律線の判りやすいイタリア風のホモフォニーにアレンジされたもの(Cantioale様式)が好まれました。これは後に讃美歌の定番的なアレンジになるものです。礼拝での実用とは関係なく様々なアレンジが試みられたのは、聖歌隊の音楽教育の対象としても編まれたことを示します。逆に改革派教会は多声的なアレンジを全く認めず、むしろ少年のよく通る声を先唱に用いるように指示しています。作曲家が多声曲へのアレンジを施す場合には、ジュネーヴ以外の地(リヨンやパリ)で印刷にかけました。しかしいずれの場合もオルガンや様々な楽器を用いずに人の声のみで礼拝することは、初期の宗教改革者に共通する理想の状態であったようです。 [NEXT→] |
||