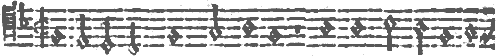 |
||
| 明治〜大正期の歌謡芸能 明治期の讃美歌では歌唱法の問題はあまり取り上げられませんでした。これは不思議に思われるかもしれませんが、讃美歌を歌えること自体が信仰の表明になり得た、極めて融通の利いた時代であったともいえます。極初期には音程そのものが判らず、オルガンの補助によってようやくメロディを歌えるという程度でしたが、宣教師の家から讃美歌の声が聞こえることは伝道の灯でもありました。明治末期になっていくに従い尋常小学校唱歌でも行われたように、当時の讃美歌においても和洋折衷のスタイルが吟味されていきます。別所梅之助や松本ゑい子の例はこうしたスタイルのなかでも別格の品性を持っていたといえます。当時の人々に好まれたメロディには長唄によく似たスコットランド民謡の節回しがありますが、これを当時の人がどのように歌ったかはあまりよく判ってはいません。年代的には日露戦争から関東大震災までの四半世紀の時期に当たりますが、単純に言えることはその頃の歌い方は音楽教育の発達に伴い忘れられていったということです。これらの変換のうちには産業革命の洗礼をうけて軍国主義への道筋を辿った昭和期の歩みも含まれます。そして会衆讃美の座も変化を伴ったのではないかと思われます。ここではまず当時の録音資料を基に考察してみたいと思います。 まず洋楽受容の創生期でよく話題になるのが、三浦環や藤原義江のように海外のオペラ・ハウスの活動を日本に持ち込むことを目指した人々です。この時代で藤原義江の声量が突出しているのは、世界的にも早い時期にイタリア経由でロシア歌手の発声法を取り入れているからであろうと思われます。イタリア人教師A.サルコリ門下の原信子なども同傾向があります。一方で日本歌曲の分野での録音では、平井英子など子供による童謡の録音は別として、女声の録音では比較的口蓋を狭く使う19世紀ドイツ風の発声法の影響が強く感じられます。一般には口を大きく開けて歌うという指導法なのですが、実際には咽を狭めて歌うということになりやすい発声法です。口をパクパク大きく動かすため発音は不明確なのも特徴です。当初は海外組が日本語発音のミスマッチに悩み原語でのオペラ公演にこだわる一方で、日本における芸術歌曲の分野では大衆音楽とは別の方向で模索が続いていたことになります。なかには流行歌として歌い崩しに成功している例もありますが、大衆音楽の舞台芸人に比べ発音の聞き取りの難しいのが多いことも確かです。 唱歌や童謡の類は中山晋平によって和洋折衷の極みに達しますが、教会においては日曜学校讃美歌にその成果が受け継がれることになります。逆に大人向けの讃美歌では大衆音楽に流れていくようなことが嫌われる傾向にありました。単純には子供が童謡なら、大人は花柳界に関わりのある唄が多かったので、そうしたことを公に歌うのが好まれないという理由がありました。山田耕筰の童謡では宮下姉妹の他に、金子一雄の子供離れしたセンチメンタルな歌唱もあります。当時は古河政男の感傷的な歌でも藤山一郎や東海林太郎のように感情を荒立てずに素直に歌われ、昭和歌謡のセンチメンタルの感じ方について知る手掛かりになります。何事にも実直に向き合ってというのが心情を吐露する方法だったのかもしれません。讃美歌には感傷的な詩も少なくなく、ロマン派特有というよりは信仰覚醒期のGloomy(陰鬱)な雰囲気の名残をもっていますが、歌舞伎においても悲劇の題目が絶えないように、センチメンタルとは一種の庶民的な好みに属するようです。 舞台芸能では、浅草オペラや宝塚歌劇団のように大衆的なミュージカルからの影響が強い人々が居ました。どちらかというと演技や踊りも兼ねて評価されることが多く、歌唱法そのものは素直を絵に描いたような歌い方です。中山晋平の現われる前の大正期の和洋折衷的な流行歌には、バイオリンを片手に歌本を売っていた書生節の歌い手が居ました。彼らの歌い方は江戸の辻芸人の伝統を色濃く受け継いでいます。書生節や浅草オペラの歌い方は全体に浅い声の出し方ながら、言葉の発音が明解でマイク無しでもよく通る声を出しています。書生節は今の民謡歌手のように歌の巧さを引き立てるようなことは避けて、道端で誰もが歌詞を満遍なく憶えていくことを目的としているので、ビブラートや小節を強く掛けることはほとんどありません。彼らの歌い口から讃美歌の歌い方を想像するのは難しいように感じますが、19世紀初頭の英米のボードビリアンと比較すると判りやすいです。明治期の日本の舞台芸人が欧米公演で人気を博した理由は、実際にその演技力や歌唱力が当時のボードビリアンと遜色なかったからです。ただ日本においては一般的に讃美歌はクラシック音楽と同様に洋楽の中心と考えられ、西欧で歴史的に辿った大衆音楽としての座に思い及ぶ人は少なかったと考えられます。しかしこの時代の洋楽といえば、ありとあらゆるものが揃っていたことは記憶してしかるべきだと思います。 讃美歌と洋楽の緊張関係 当初、讃美歌の編纂は欧米並の分量を日本語で歌えるように揃えるということにありましたが、今の時代から振り返ると当時の日本文化との対話のあったことが伺えます。 ひとつは文語調でありながら個人的な心情を綴る文体の整備で、初期の讃美歌が動詞主体の武者言葉で訳されていたのに対し、体言を主体にすることで訳語の語彙を的確に凝縮して、連綿と情緒を継続するようになっています。これは明治期の讃美歌が語彙の密度の非常に高いことを示していて、歌謡曲と違いサビの部分がない、まさに息付く間のないほどに詩が展開されます。もちろん歌のサビとはリフレイン(繰り返し)の技法が福音唱歌に取り入れられて以後のものですが、リフレイン付きの讃美歌でもやはり密度は濃いです。これは当時のキリスト教会の指導者に武家出身の人が多かったことから派生したものでもあります。 ふたつめはネガティブな意味での対話なのですが、讃美歌のほとんどは和洋折衷で商業的に成功を収めた流行歌や童謡の影響を受ける以前にほぼ完成してしまっていて、讃美歌というジャンルが大正期には古典的なものになっていた点です。これは西欧の純粋に教会的な伝統を当時の讃美歌が担っているという解釈を離れることなく、日本の讃美歌は流行を追う方向には展開することが無かったと言えます。例外的に日曜学校の讃美歌は童謡や軍歌の影響を丸まま受けて、1960年代に至っても同時代の作家が参加した経緯があります。日本の讃美歌で時代毎に代表作を挙げようと思えば、こどもさんびかの幾つかは候補に挙げてしかるべきです。逆にいえば、讃美歌のスタイルはある特定の時代様式に固執しているといえましょう。 このように肯定と拒絶の狭間にあってもなお、讃美歌は歌集として最も整備された内容と分量を誇っていたと言えます。海外ミッションの後押しがあったとはいえ、100万冊以上出版された歌集など日本の歴史のなかでも未曾有の出来事でした。まさに一家に一冊というレベルを越えて一人に一冊という配分が徹底されたのです。これは流行というより文化の一端を担っているという感じもします。しかしながら、概ね讃美歌の歌唱は歌い手の庶民性のゆえ、巷の歌謡曲との緊張関係にあったことは否定できず、長い対話の拒絶が続いた後に最終的にはクラシックの牙城に留まる決意をしたように思います。実際には庶民芸能と関わりの深い讃美歌を立派なクラシック作品に仕立てるのは無理があります。 一方で拒絶された流行歌には世代間のギャップというものが当然あって、明治から現在に至るまで4〜5世代の変換のうちに、讃美歌の楽譜そのものは変化しなくとも、緊張関係にあった歌謡曲の変化には注目するべき点が多々あります。明治初期は長唄風の歌い口だったでしょうし、大正〜昭和期には”てにをは”をはっきり発音する唱歌風の歌い方が多いように思います。戦後はフォークソングなども流行りますが、時代的に教会の社会性を批判することが多かったため、1980年代までほぼ凍結されています。新しいゴスペル・ソングが出た頃には50年間の対話の拒絶が、ジャンルの違いに至るまで異質なものに変化していたことを物語っています。 こうした緊張関係のなかでは、讃美歌がクラシック音楽の殿堂入りを果たす一方で、庶民的な感性では歌謡曲が座を占めるという、実用上のアンバランスさに問題があるように思います。これは讃美歌の作風の問題ではなく、その歌唱法の伝承において問題があったというように考えられます。 讃美歌謡の再建を目指して 一般には讃美歌は19世紀風のものが主流で、いわゆる20世紀的なモータリゼーションの影響を受けなかったと思われがちですが、実際には歌唱法の面で様々な影響が顕われていることが判ります。つまり明治期にはスコットランド民謡の節回しが好まれ、昭和期には軍隊調のカッチリした歌い方が好まれ、高度成長期にはオペラ声が会堂のステータスを握ったのです。こうした流れは多かれ少なかれ欧米においても同じことが言われ、教会における歌唱法を産業革命以前の情況に戻すことが1970年代からの課題にもなっているように思います。日本においてはキリスト教会内に歌唱法に関する文化的な蓄積がないために、こうした記憶を呼び戻すためには様々なハードルがあるように思われます。 1)大衆文化との対話 西洋における讃美歌の歴史は世俗と教会文化の対話によって成り立っています。これは教会の権威が強かったと言われる中世においても変わらない営みであったことが様々な資料から明らかになっています。一方で日本の讃美歌の座は伝統的な教会文化のエッセンスとして受け止められています。これは半分正解で半分は間違いです。重要なのは教会的とは応答的で対話的な世界だということです。讃美歌は極めて世俗的な要素を歴史的に背負ってきたし、それが教会的な讃美に高められるまで闘ってきた遺産なのです。その意味で讃美歌はいつの時代においても折衷的です。この折衷的という讃美歌の座に会衆を置いたとき、私たちの讃美の文化的な側面が明らかになってきます。日本は残念ながら讃美歌の輸入依存度が極めて高いのが特徴で、逆に歌謡文化はテレビやラジオの影響を大きく受けています。これは日本が異教文化だからという以前の問題で、讃美を通じて行なわれる世俗文化との対話の基盤が脆弱であることも示しています。 2)歌謡的な音律の伝承 もうひとつは音律の伝承の問題で、英米系の讃美歌がヨーロッパ風のミーントーンを基調にしながら、時折スコットランド的な5度の響きの強い節回しを挿入しますが、これは民族間や身分間での音律の不調和を組織音階のミーントーンで処理しながら信仰告白の場で5度の響きを強くするという、移民社会での讃美歌唱の座が歴史的に蓄積されたものです。一方で日本ではこのtemperament(音律=気質)の差から生じる讃美の座のポジション取りが伝承されておらず、そのことが明治から昭和にかけての讃美歌唱の大衆的な変化に明瞭に表われているように思います。つまり明治期にはスコットランド民謡の節回しが好まれ、昭和期には軍隊調のカッチリした歌い方が好まれ、高度成長期にはオペラ声が会堂のステータスを握ったのです。このような気まぐれな状況のなかで、もういちど音律の伝承ルートを掘り返し会衆に認識させ、次の世代に引き渡すには時期が遅すぎたとも考えられます。つまりこの伝承から新しい讃美の理解は生まれない可能性が高いのが悩ましいところです。それは世界的にも音律の特徴は著しく平均化されていて、少数言語の消滅と同じく音楽文化継承の母胎となる音律の種類も非常に限られてきているからです。 3)自然で明瞭な言葉づかい 声の大きさを競う歌唱指導ではなく、声の多彩な響きの変化に注目するように仕向けること、そして歌詞を明瞭に鳴り響かせるという基本に立ち帰ることが大切なように思います。例えば語幹は明瞭に発音する一方で、語尾や接続詞は鼻に抜けるように曖昧に発音するなど、話し声では当たり前にやってることをマイクを通さずにできるようになることです。やはりこれにも話術を補佐する筋肉のトレーニングを積み重ねる必要があります。同じような問題性は日本歌曲や童謡の歌手からも発題されていて、肉声による歌謡の衰えというものを取り戻す考えは共通しているようです。 声が大きく出ないので私は讃美が下手で、という人は大勢います。これは実際には誤った見解で、小さな声でも十分に巧く歌えるものです。豊かな讃美とは持って生まれた才能ではなく、信仰の経験を歌で表現できることだと思います。その表情を効率的に動かす方法は色々ありますが、さらにその表情を会衆全員が合わせるということが、心のこもった讃美になりはしないでしょうか。各々の声量に合わせて精一杯コントロールした讃美が良いのです。 実際の歌唱においてどうすべきか、まだあまり結論は出ていませんが、時代考証において逆ルートを辿っていこうかと思っています。まずは昭和歌謡→浅草オペラ→唱歌という順序になっていくように思います。 ♪日暮れて闇は迫り(讃美歌21 218番) イギリスの讃美歌で夕刻に合わせて歌うものです。日暮れの頃の風情と 19世紀的なロマンティックな抒情性とが巧く折り重なった讃美歌です。 ここではミーントーンの人懐っこい表情と、言葉の抑揚に留意しながら 大正ロマン風の歌い方に近づけてみました。押韻にも気を遣ってください。 ♪やまべにむかいて(讃美歌301番) 別所梅之助が大正期に書いた讃美歌です。登山家としても知られた 別所の山に向ける思いは遙か天にあったかと思うのです。 詩篇121篇に寄りながら、ピューリタンのGloomyな文脈も忘れてません。 前半はミーントーンで甘めに、後半はピタゴラス的なかっちりした音程で 人の思いの内証性と神の救いの客体性のドラマを作ってみました。 言葉の繊細さとほのかなロマンティシズムを織り混ぜています。 ♪「あまつましみづ」都々逸風 永井ゑい子作「あまつましみづ」に都々逸風の節をあえて付けてみました。 少し俗過ぎる面がありながら、ちゃんと歌詞の韻律が浮き出てきます。 オルガンでの歌唱指導 19世紀後半に広まったリード・オルガンの作り出す安定したハーモニーは、民族の違いによる音律の交錯を見事に解決しました。特に日本における西洋音楽の導入に果たした役割は計り知れないでしょう。ただリード・オルガンから音律を伝承された際に、実際の歌唱のほうは棒歌いになる傾向が多いようです。これは”オルガンに声を合わせて歌う”という明治時代からの指導法からくるもので、実際には讃美歌には色彩豊かな歌謡の世界があります。ただメロディの線を直線的になぞるだけでは歌の表情を得られません。音律がこわばった歌い方では、逆に歌の表情を声質で伝えようとするため、声を豊かに張り上げることが歌の上手い人という誤解も生まれてきます。豊かな讃美とは持って生まれた才能によるのではなく、信仰の経験を歌で表現できることだと思います。その表情を効率的に動かす方法は音律やリズムの設定にあります。その表情を会衆全員が合わせるということが、心のこもった讃美になるのです。とくに30名程度の教会が多い日本の実状では、会衆がオルガンに歌を合わせるというよりも、互いに歌の表情を聴きあって、各々の声量に合わせて精一杯コントロールした讃美が良いと思います。なので会衆讃美の伴奏ではオルガンの音で会衆の声を無理に引張るのではなく、音律の動きやテンポの揺らぎを許容できる余地を十分に残しておくのが良いように思います。 いわゆる”オペラ声”の問題点 オペラ歌手が讃美歌を歌う例も商業録音では少なくありませんが、普段から礼拝奉仕に熟練している聖歌隊の歌い方とは言葉使いが異なります。いわゆるオペラ声もある意味では大衆的な願望だったのですが、教会の会衆讃美の座に君臨することはあっても仕えることはありません。あたかもオペラの主人公が個人のパーソナリティを舞台で浮き立たせるようにする方法をそのまま背負ってきてしまい、一方ではそこに埋もれている真の会衆の姿が背景に押しやられてしまうのです。これは一見して歌唱法の発展と思える事柄が、実は会衆に歩調を合わせずについていけない方向へと目標を定めてしまったと思えるものです。讃美歌=西洋文化の魂→西洋音楽の頂点=オペラという図式があまりにも単純で、安易に理解できた西洋音楽の知識だったと言えましょう。オペラ風に豊かな声で讃美することは、声を出す人の存在感は引き立てますが、讃美歌の内容を伝える技術の未熟さが多く残り、歌唱技術についての多くの誤解を生む原因にもなっているように思います。 |
||
| 現在進行中の課題 戦前の日本語歌唱の録音をもとに問題点を整理する 西欧の16世紀と19世紀の歌唱法の研究をベースに最適化を模索中 世代毎に歌謡曲の影響が大きいなかで教会の歌唱法を継承する方法を考える |