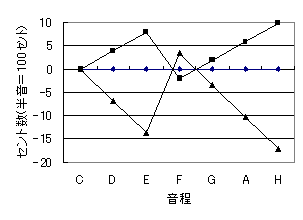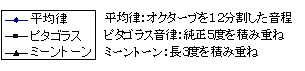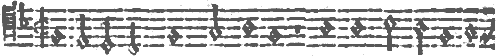 |
||
| 移民社会での歌謡の多様性 アメリカでの讃美歌の変換を辿るとき、戦争を通じて地域文化の交流が盛んになり特定の情況に集約されていく過程があると思っています。 1.独立戦争以前のピューリタン社会での歌謡 無伴奏で甲高い声を張り上げる歌い方 2.独立戦争以後から南北戦争までのロマン期 ドイツの古典派からロマン派の影響を受けた歌謡 3.南北戦争から第二次世界大戦までの近代化 オルガンによるハーモニーの固定化とフォーク・ソングの枝分かれ 4.第二次世界大戦以後のコンテンポラリー・ミュージック ジャズやロックなどの影響を受けたバンド演奏を伴う歌謡 これらの時代区分において、日本の讃美歌が受け持っているのは3の時期のみで、あるいは4の方法で讃美礼拝を採っている教会もあるでしょう。ここでは1〜3の時期の歴史的な歌唱法を問題にすることにします。 |
||
| A.歌い手の問題 音律の扱い 歌謡の要の多くは音律(temperament)によっています。特に19世紀の歌謡では民族音楽を汎用的な音律(Well temperament)に適合させる努力がなされたものの、それは同時に曲毎の気質(temperament)を強調する手段としてポルタメントなどを加えて歌い崩す即興性にも繋がってきます。中世〜ルネサンスの聖歌は教会堂という残響の長い場所で演奏されるように作られ、音律は旋法に従ったハーモニーの問題として処理されますが、19世紀の讃美歌は家庭音楽の響きに合わせられている傾向があり、メロディ間のハーモニーの変化を拍節に区切った機能和声に置き換える傾向があります。17世紀のイタリア・バロックにおけるミーントーンの扱いは、通奏低音に折り重なるようにハーモニーを展開していくものでしたが、19世紀ロマン派のミーントーンは機能和声のハーモニーを歌い崩すことでメロディが和声のモードで分断されることを慎重に避けています。そしてそのことが19世紀の讃美歌の歌謡性を高める要素になってくるのです。音律にはメロディの要となる間接のようなところがあるのですが、その間接を中心にメロディを巧く動かすことによって滑らかな動きが生まれきます。ただメロディの線をなぞるだけでは歌の表情を得られません。 西洋音楽で平均律が完全に定着するのは19世紀末のこと(マーラーが平均律で響きの色彩感が失われたのを残念がっている)で、モーツァルトやヘンデルはミーントーンと呼ばれる3度の響きを重視した音律を好んだと言われます。ベートーヴェンはキルンベルガー的なカッチリした音律によって作品が引き立ちますが、ヴァイオリン・ソナタはミーントーンに近い音律で書かれたのではないかという説もあります。ショパンは自身の作品の演奏に調律の異なる数台のピアノをコンサートで用意したそうです。ヴァイオリンの流派でも、フランコ・ベルギー派の甘いミーントーンと、ハンガリー出身のヨアヒムやアウアーに連なるクールで端正なスタイルとでは、同じ作品を弾いても雰囲気が大きく異なります。これらを照らし合わせると17世紀から19世紀前半までは、ミーントーンを中心とした音律が支配的だったことが判ります。こうしたことはそのまま近代の讃美歌の歌唱スタイルにも結び付いてきます。私は19世紀に作曲された讃美歌は押し並べてミーントーンで歌うべきだと感じています。ミーントーン独特の妙に人懐っこい表情が初期ロマン派の市民像にぴったりくるのです。 ♪日暮れて闇は迫り(讃美歌21 218番) イギリスの讃美歌で夕刻に合わせて歌うものです。日暮れの頃の風情と 19世紀的なロマンティックな抒情性とが巧く折り重なった讃美歌です。 個人的に歌いやすいようにピッチを上げて歌ってみました。 ミーントーンは平均律に比べ少し垂れ下がった感覚があります。平均律の楽器が多い現在でミーントーン自体は判りにくい音律かもしれませんが、例えばカントリー歌手は極端にメロディをフラット(♭)に採ったりして、デュエットで綺麗なハーモニーを奏でます。サイモン&ガーファンクルは、ガーファンクルがミーントーンで上に乗ることで綺麗なハーモニーを出しています。驚いたのはボブ・ディラン(ブルース、ロックの歌手)のコンサートに、ジョーン・バエズ(カントリー歌手)がゲスト出演したときのことです。既に平均律で歌うことに馴れた都会派のディランに対し、極端なウェスタン風のミーントーンで歌うバエズの音程とが全く噛み合わないでデュエットを進行していました。こうしたことを例にアメリカでの歌謡の違いを押さえておくのは有意義だと思います。
逆に英米の讃美歌で気を付けなければならないのは、アメリカのキリスト教に通底するピューリタンの影響で、歌唱法としては甲高い声を長く張り上げるスタイルを持っています。特に18世紀のアメリカの讃美歌ではこの傾向が強いのですが、19世紀においても野外伝道集会の伝承を引き継いだ讃美歌には残っています。今でもイギリスのサッカー場でサポーターがウォ〜オォ〜と会場全体が波打つように歌っているのが聴かれますが、あの感覚が19世紀の讃美歌のなかにも含まれているのです。このときの音律は極端にペンタトニックの傾向が強い硬い音階で、場合によっては荒々しい不協和音が生じることがあります。これを逃すことで歌全体がメリハリのない感じに陥ってしまうことがあるので、適度に声を外す箇所をしっかり押さえておく必要があります。 声質のコントロール 現在のオペラ歌手のように胸声に共鳴を加える歌唱法が現われたのは、最も早い時期でも19世紀の前半で、バロック的な細かいコントロールが必要な楽曲から、ストレートなメロディを力強く歌う曲に変換していった時代にあたります。ロマン派作品で胸声を常に響かせる発声法は、声の響きを豊かにし歌い手の存在感を浮き立たせる一方で、十分なコントロールができるまで訓練された人は極少数です。実際に欧米のコンサート歌手の間では1910年代から1930年代に掛けて急激に発声法が変化したことが挙げられ、一般にはロシア革命により流出した歌手兼音楽教師の影響だろうと言われています。アメリカにおいてロシア的な歌唱法を学ぶようになるのはナチス・ドイツがヨーロッパ支配を始める1930年代以降に、ロシア人亡命者がアメリカに流入するようになってからです。この前座としてメトロポリタン歌劇場でのメルヒオールやフラグスタートなどの北欧歌手の活躍があり、フィンランド、スウェーデンでのロシア人歌手の教師の成果が圧倒的に示されたのでした(同じようなことは20世紀のピアノやバイオリン演奏についてもいえます)。その後、英米出身の歌手が煩雑にクラシックのレコーディングに駆り出されるようになるのです。そういう意味で欧米と日本の声楽の差が付き始めたのは1930年代が境目のようであり、単純に日本人の体格ではクラシックの発声法が難しいと言われ始めたのも戦後の時期に当たります。これは西欧人と東洋人という違いというよりは、発声法を学ぶルーツが20世紀に入って変わってきたと考えるのが普通のように思われます。讃美歌のメロディは全般に平坦なため、胸声を強く響かせる歌唱に向いていますが、作曲当時はそういう意図がなかったことに留意する必要があります。 このようなロマン派特有と誤解されてきた歌唱法は、多くの讃美歌の作曲された19世紀前半のものとは違う19世紀末のものであり、教会での讃美歌の歌唱に与えた弊害も少なくありません。単純には訓練を受けた綺麗な声であることがステータスになって、言葉の発音が不明瞭なことが多く、発声の問題に限っていえば目的よりも手段に呑まれて安んじている人が多いのです。これは讃美の本来の目的からずれていると言わざるを得ません。音楽的な解釈では18世紀の英米讃美歌なら発声時にスナップを効かせた声の出し方が多いですし、19世紀なら民謡的な節回しをチャーミングにこなすほうが効果的であると思います。また日本語の発音において声帯の共鳴を平たく抑えることで明瞭になる場合もあり、日本人が一般に習う西洋的な発声法(その多くは声量を大きく出すことに終始します)に比べ、より柔軟でダイナミックな表現が求められます。これは歌詞のコントロールが周到に準備されて初めて出来ることなので、声が大きく綺麗に歌えただけで満足せずに、歌詞の意味と表現が一致したときに喜ぶ習慣付けが必要になります。 民謡と踊り 19世紀の讃美歌で大衆的なニーズに応えるものとして、当時としては大胆に民謡の節回しをあしらったり、踊りのリズムを持ち込んだものがあります。例えば「飼い主わが主よ」や「主われを愛す」にヨーデルの節が含まれています。ヨーデルの節は19世紀後半には白人ブルースに頻繁に出てくるのですが、楽譜として残ったものではこれらの讃美歌が最も早いものだと思います。また踊りの面ではワンステップ、ツーステップの踊りが時折みられます。ヤトトトやヤトト、トトのリズムが出てきたら要注意です。「喜ばしき声ひびかせ」の後半部、「あまつみつかいよ」の前半部などがそうです。いずれも18世紀のメソヂスト教会がキャンプ・ミーティングで用いたものと思われますが、踊りの節と入れ違いにピューリタン節が出てきますのでこちらも参考にしてみると良いでしょう。全く異なる楽想を組合わせたものなので、両者を同じテンポに合わせる必要もないように思います。 B.伴奏者の問題 オルガン伴奏での歌唱 19世紀後半に広まったリード・オルガンの作り出す安定したハーモニーは、民族の違いによる音律の交錯を見事に解決しました。特に日本における西洋音楽の導入に果たした役割は計り知れないでしょう。ただリード・オルガンから音律を伝承された際に、実際の歌唱のほうは棒歌いになる傾向が多いようです。これは”オルガンに声を合わせて歌う”という明治時代からの指導法からくるもので、実際には讃美歌には色彩豊かな歌謡の世界があるのです。日本の教会において讃美歌の指導を行うのはオルガニストである場合が少なくないのですが、声の大きさと音程以外に、言葉の発音と音律の設定を簡単に指示できると便利かと思います。とくに30名程度の教会が多い日本の実状では、会衆がオルガンに歌を合わせるというよりも、互いに歌の表情を聴きあって合わせるほうが良いように思います。なので会衆讃美の伴奏ではオルガンの音で会衆の声を無理に引張るのではなく、歌唱のコントロールできる余地を十分に促すのが良いように思います。 電子オルガンの扱い 非常に広範に行き渡っていたリード・オルガンですが、歯並びの悪い音程でブーカ、ブーカ鳴ってるのを思い浮かべる人も居るかも知れません。最近ではリード・オルガン自体が高価で手に入りにくいのと、調律のできる人が少ないこともあって、電子オルガンに切れ変わる傾向があります。電子オルガンは第二次世界大戦を前後してレスリー・オルガンが広く行き渡り、1960年代のムーグ社のシンセサイザー式キーボードで音色のパレットに大きな進展が顕われます。最近のものは1980年代以降のPCM音源を用いた第3世代のものになります。 ただ電子オルガンを持つ教会に行くと、決まって会衆はカッチリと棒のように声を出す傾向があります。電子オルガンがアコースティック楽器と決定的に違うのは音に流れがないことです。アコースティック楽器では必ず音の始めと終わりに、基音以外の倍音を伴ったアクションや減衰に伴う共鳴音の変化が付随し、メロディの方向が把握できます。むしろ19世紀の音楽はそういう機能を前提に譜面のアレンジが施されています。1970年代の初期のシンセサイザーが空間エフェクトのようなドローンを流すようにアレンジされていたことを思い浮かべてみるのもいいでしょう。電子楽器の再生能力ではこのアクションや共鳴音が著しく乏しいので、会衆は声をまっすぐ伸ばす方向でオルガンの音に対抗しようとします。パイプ・オルガンを真似た立派な楽器でもやはり情況は同じです。独立したオルガン作品を弾く場合と会衆讃美の伴奏では弾き方を換える必要があります。 電子オルガンは拡声器の機能も持っていますが、音量そのものが礼拝堂に合ってないときもありますので比較的抑え気味の状態を保持して、必要最小限に会衆にハーモニーを促す程度のほうが良いでしょう。スピーカーの性能の限界でベース・ラインの音程が不明瞭でハーモニーがダブつくことも多く、あまり大袈裟な重低音の補強は会堂の響きに一種の圧迫感を与えます。逆に讃美歌の伴奏の際に、足鍵盤を放棄して音量ペダルを使って注意深くフレーズをコントロールしている人も居ます。また電子楽器の共鳴音の不足を補うため、ピブラートを掛ける人も居ますので参考にしてみると良いかもしれません。機能満載で至れり尽くせりの電子オルガンですが、実際には電子オルガンのほうが細かいコントロールの必要な気がします。 その他の楽器 アメリカでは教会の聖歌隊組織がヨーロッパのバロック期のように整備されませんでしたから、世俗的なアイディアを詰め込んで実に色々な楽器で讃美歌を演奏していました。ギターはともかく、フィドルをかき鳴らしたり、軍楽隊のマーチ風に編曲されたり、果てはオルゴールの例もあります。オルゴールは終わりにちゃんとアーメンの伴奏まで付いている可愛らしいものです。ギターを例にとっても、19世紀末のフォークソングの仕様でスチール弦とピックを用いるか(通常のピックよりも長いナイフを用いてフィドルの音程感を出す奏法もあります)、19世紀初頭のフランスやイタリア製の小型ギターで伴奏するかでは、かなり様子が変ってきます。18世紀イギリスのメソジスト運動期のギャラリー・バンドを模した演奏もありますが、ミンストレル・ショーほど砕けたものではありませんが、クラリネットやバイオリン、小太鼓なども加わってそれと似た感じでもあります。この辺のアメリカ特有のフォークロアはまだ情報をあまり多く持っていませんが、最近になって南北戦争以前の奏法や歌唱法をColonial Musicとしてクローズアップする傾向があるので、色々と資料を集めて検証してみようと思っています。 |
||
| 現在進行中の課題 1.声量と表現力の識別を明瞭にする 声量の保持よりもメロディの流れを作り出す運動的な歌い方を提案する 日本語の発音をなめらかにコントロールできるように随意訓練中 個人的な感情表現を会衆讃美の奉仕の座に結び付ける習慣をつける 2.ロマン派の歌謡へのアプローチ 主知的な感情表現を歌い方として客観視できる環境を整える 民族的な歌唱法を即興的に織り交ぜる演劇的要素を模索する ミーントーンと機能和声のバランスを正しく把握させる |